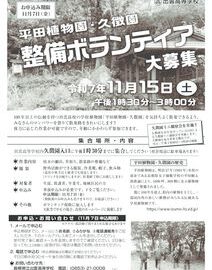今年の8月は酷暑に加え雨が少なく、人にとっても植物にとっても厳しい夏でした。
8月に撮影した久徴園の草木花を紹介します。
(画像はクリックすると拡大できます。)

ワレモコウ(バラ科ワレモコウ属)
晩夏から秋にかけて、濃い紅紫色の球状花序(小さな花が集まった形)をつける姿が風情を感じさせ、生け花にもよく利用されます。名前の由来は「~もまた」を意味する「亦」を「も」と読み、「吾亦紅」とか、インド原産の木香に花が似ることから、「吾木香」など諸説ありますが、定説はありません。近年は4~5号館の間の中庭にたくさん咲きます。

キンミズヒキ(バラ科キンミズヒキ属)
黄金色の細長い花の連なりが、金色の水引(熨斗や祝儀袋につける飾り紐)に似ていることから、「金水引」と名付けられました。名前の似るミズヒキはタデ科で、バラ科であるキンミズヒキとは異なる仲間です。果実にはかぎ状に曲がった棘があり、服や動物の毛にひっついて拡散されることから「ひっつき虫」ともいわれます。ロックガーデンに咲きます。

センニンソウ(キンポウゲ科センニンソウ属)
和名は花の後、瘦果に付く綿毛を仙人の髭に見たてたことに由来します。別名が「ウマクワズ(馬食わず)」、有毒植物で馬や牛が絶対に口にしないことを意味します。茎や葉の汁は触れると皮膚炎の原因になります。正門坂に咲いています。

タカサゴユリ(ユリ科ユリ属)
ラッパ状の花を咲かせるユリ科の植物、夏になると校内の至る所に咲き乱れます。台湾原産の外来植物で、観賞用として大正時代に日本に入ってきたといわれます。似た花のテッポウユリは花がやや小さく紫色の筋が入りません。葉もタカサゴユリは細長く、テッポウユリは笹の葉のようにやや膨らみがあります。